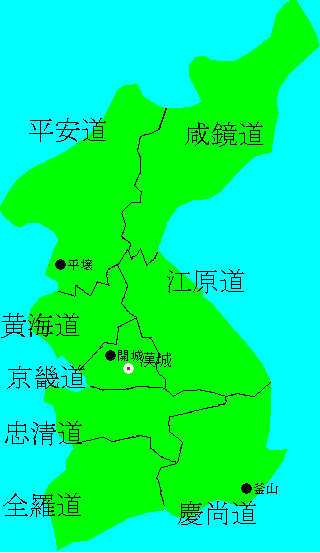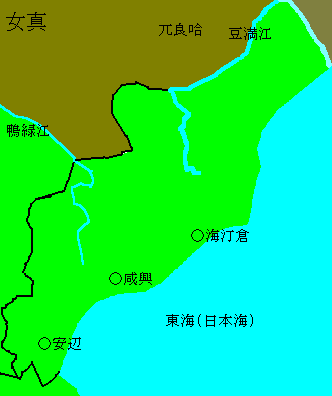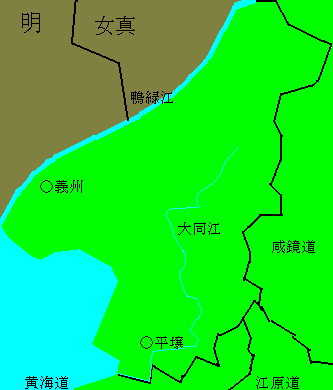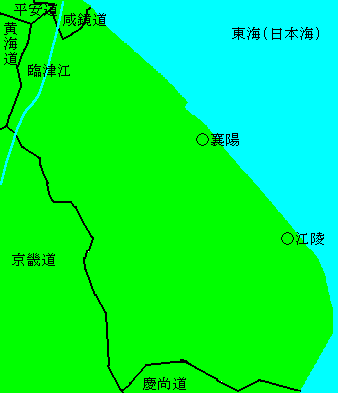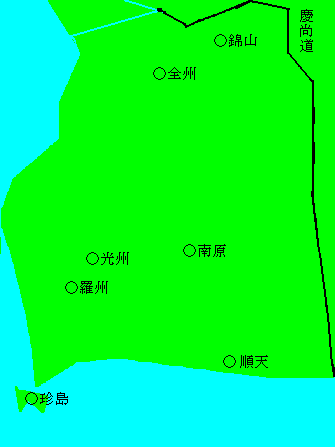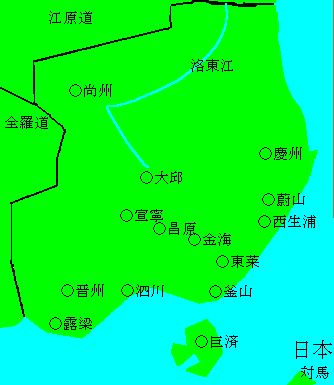|
慶尚道(キョンサンド:경상도)
|
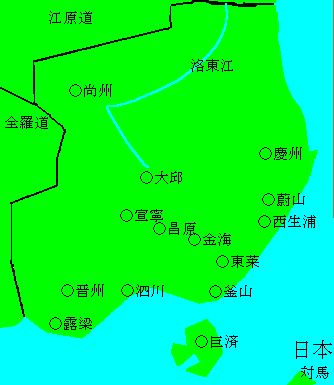 |
朝鮮側守将 | 武将:李舜臣(イ・スンシン、り・しゅんしん)、鄭發(チョン・バル、てい・はつ)、李鎰(イ・イル、り・いつ) 、元均(ウォン・ギュン、げん・きん)、宋象賢(ソン・サンヒョン、そう・しょうけん)、金時敏(キム・シミン、きん・じびん)
義兵将:郭再佑(クァク・チェウ、かく・さいゆう)、成安(ソン・アン、せい・あん)、鄭仁弘(チョン・インホン、てい・じんこう)、金沔(キム・ミョン)
明将:麻貴(マク・ウイ、ま・き) |
| 日本側攻将 | 小西行長、加藤清正、藤堂高虎、加藤嘉明、島津義弘、脇坂安治、宇喜多秀家、細川忠興 |
| 予定占拠者 | 毛利輝元 |
| 主要府鎮 | 東莱(トンネ)、蔚山(ウルサン)、尚州(サムジュ)、晋州(チンジュ) |
| 主戦場 | 蔚山(ウルサン)、晋州(チンジュ)、露梁、巨済島(コジェド) |
日本領対馬の対岸、という地理的必然もあって日本軍の上陸地となり、最初の開戦地となった上に数々の激戦が展開されたのがこの慶尚道であった。必然日本・朝鮮供に多くの将がここで戦い、命を落とした者も多い。
釜山に上陸した日本軍の進撃を受けた鄭發が戦死、次いで東莱でも宋象賢が討死した。日本軍は優れた鉄砲で泰平になれて戦意の低い朝鮮官軍を次々に打ち破り、開戦から二週間を経ずして尚州の李鎰も敗れ、朝鮮軍は半月足らずで慶尚道の突破を許してしまった。
しかし時をほぼ同じくして李舜臣率いる水軍は藤堂高虎・脇坂安治・加藤嘉明といった日本水軍の猛者達を日本軍の不慣れな面の戦いに持ちこんで次々に撃破し、補給困難をもたらして戦の不利を取り返した。
また度重なる日本軍の蹂躙は義兵も数多く起こるもととなり、最強の義兵将・郭再佑を筆頭に鄭仁弘、金沔等が日本軍を悩ませた。
慶尚道が激戦の地となったのは日本と明の間で講和交渉が行われる際にここを押さえているかどうかがネックとなったために秀吉が意地になって奪取を厳命したこともその背景にあった(時代は異なるが、日露戦争でも樺太を占領していたことがポーツマス講和会議を日本有利に進めたという例がある)。
殊に晋州は文禄元(1592)年一〇月に金時敏が細川忠興を撃退するも、文禄二(1593)年六月に総大将・宇喜多秀家に加藤清正・小西行長といった先鋒諸将までもが加わった猛攻を受け、金千鎰も巨木・岩石・熱湯を駆使して応戦したが、ついに黒田長政配下の猛将・後藤又兵衛が城壁を破り、金千鎰が戦死しただけでなく、城兵は全滅し、日本軍も少なからぬ損害を被った。
文禄の役から慶長の役の過渡期にあっても日本軍は多数慶尚道に留まった。全羅道に侵入できなかったから尚更である。
慶長の役が始まると当初は讒言にあって失脚した李舜臣を欠く朝鮮水軍を加藤嘉明勢が大いに打ち破り、元均を討ち取ったが、舜臣はすぐに復帰し、再び水軍の優位は逆転した。
陸上では休戦中に日本軍が守りを固めた蔚山を落とすことが戦の命運を左右すると見た明将・麻貴率いる援軍が酷寒と兵糧不足に悩む加藤清正を散々に苦しめるが、清正は毛利秀元が救援に来るまで寡兵ながらもよく持ち堪え、城を守りきった。必然この戦いでも両軍に多くの犠牲が出た。
慶長三(1598)年八月一八日に豊臣秀吉が薨去するに及んで慶長の役は終ったが、戦そのものは三ヶ月間継続された。殊にこの慶尚道では日本軍が撤退に際して釜山に集結して対馬に向かって退いたため、島津義弘が泗川で陸上最後の、露梁で海上最後の戦いが行われ、島津勢の撤退を持ってすべての戦闘が終了した。尚、この露梁海戦で終始に渡って日本軍を苦しめ、救国最大の英雄とされた李舜臣は日本軍を打ち破るも、自身は壮絶な戦死を遂げ、大いにその名を挙げた。
現在釜山には李舜臣の立像が日本を睨む形で立てられている(他にも各地に立像は立てられている)。 |