| 反故にされた人物 | 吉川広家(及び間接的に毛利一族) |
| 反故にした人物 | 徳川家康 |
| 反故にされた瞬間 | 慶長五(1600)年一〇月二日 |
| 反故にした背景 | 豊臣恩顧勢力削減 |
| 卑劣度 | 五 |
| 騙し度 | 九 |
| 止む無し度 | 五 |
| 反故のツケ | 幕末に至って長州藩は倒幕に尽力(及び岩国冷遇) |
秀吉の遺命(許可無く大名間の婚姻を禁じたこと等)を破り出した家康に対し、五大老の他の四名は前田利家を筆頭に家康を詰問した。
そして四大老の中には毛利輝元もいた(後の二人は宇喜多秀家・上杉景勝)。
前田利家の余命は幾ばくも無い、と見た家康は事を構えるのを避けたが、慶長四(1599)年閏三月三日に前田利家が薨去すると家康は豊臣家臣の武断派(主に加藤清正、福島正則等、子飼の猛将や黒田、細川等の様に古くから秀吉に従った大名)と文治派(主に石田三成、長束正家等五奉行や小西行長等の様に長浜時代から秀吉に従い出した家臣)の対立を裏で糸引いたり、前田利常や上杉景勝を挑発したりして、敵味方の見極めを謀りつつ、秀頼の名で自らの邪魔となる勢力を駆逐する機会をうかがった。
周知の様に、一連の謀略に上杉景勝・直江兼続が反発し、これが天下分け目の戦い・関ヶ原の戦いに繋がり、事実上の大将として石田三成が立ち上がった。
だが三成は彼に人望が無い、と断じた莫逆の友・大谷吉継の苦言を聞き入れ、五大老の一人・毛利輝元を総大将に、同じく五大老の一人・宇喜多秀家を副将に立てた。
だが百戦錬磨で老獪な策謀家でもある徳川家康に、そこそこの才能はあっても身内の協力を得て何とか大身を果たしてきた輝元が大将として抗するのは「不利」と考える人間と、家康を滅ぼして豊臣政権下における毛利家の地位を高める「好機」と捉えた者とがいた。
前者の一人は吉川広家(きっかわひろいえ)だった。
吉川広家は永禄四(1561)年一一月一日に吉川元春(毛利元就次男)の三男として生まれた。
父・元春は叔父・小早川隆景(元就三男)とともに当主・毛利隆元(元就嫡男)及びその嫡男・輝元を補佐し、元春・隆景による宗家補佐体制は「毛利両川」の名で有名である。
父・元春の後は元春嫡男にして広家長兄である元長が継ぐ事が決まっており、次兄の元氏は繁沢氏に養子に行っていた(に毛利に復姓)。三男に生まれた広家は猛将としての資質を持つ父・元春や長兄・元長よりも謀将として長けていた祖父・元就に似たらしく長じて謀に長けた。
そんな広家は、幼少の頃は「うつけ」と呼ばれ、父を嘆かせたり、分家三男の立場から広大な所領を継げないと見て両親にも告げずに他家の養子になろうとして両親を激怒させた事もあった。
天正一一(1583)年に叔父・秀包(ひでかね:元就九男)とともに羽柴秀吉の元に人質に出されるも、これは名目らしくすぐに返された。
天正一四(1586)年に父・元春、翌一五年に長兄・元長が九州征伐従軍中に相次いで病死し、期せずして吉川家当主として月山富田城と出雲一四万石の所領を継承することとなり、広家を名乗り出した。
以後秀吉の命で肥後国人一揆征伐、朝鮮出兵に活躍し、秀吉から高く評価され、羽柴姓と侍従の官位を許される一方で、人質として差し出していた娘を秀吉が引見しないという冷遇された面もあったりした。
だが、その頃になると元春・隆景が務めた両川体制を毛利秀元(毛利元就四男・穂井田元清の子)とともに担う様になっており、その手腕はそれなりに評価されていた。
父・元春と叔父・隆景が両川を務めていた頃に比して、広家と秀元がメインとなっていた輝元支援体制は明らかにブレーンとなる人材での思考方針で統一性を欠き、後々、そこを徳川家康に突け込まれたのであった。
参考:毛利家家系図
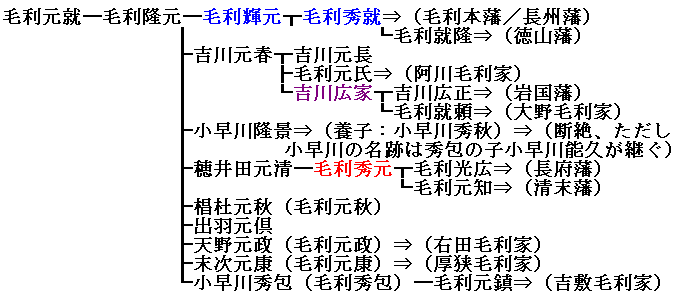
慶長五(1600)年の関ヶ原合戦時の毛利輝元のブレーンは従弟である吉川広家、毛利秀元、使僧・安国寺恵瓊(あんこくじえけい)だった訳だが、上杉景勝討伐に出陣した家康に対し、その間隙を縫ってこれを討たんとした石田三成が挙兵した。
安国寺は三成に協力して輝元の五大老ナンバー1の地位を獲得せんとし、秀元はいずれに付くかより毛利の武威を天下に示すことに腐心した。
そしてもう一人のブレーン・広家は家康とは戦うべきではない、と考えた。
毛利家・吉川家の悲劇は意志統一が為されないままにブレーン達が個々に動いたことにあった。
豊臣家の為に何としても家康を除くべし、との信念に燃える三成は、親友・大谷吉継の思い止まる様に、との説得に耳は傾けても従わなかった。止まらない親友とともに死ぬ覚悟をした吉継は、三成の為に、普段から生真面目過ぎる三成に人望がないことを挙げ、近江佐和山一九万石の中堅大名の家格では家康に抗し得ないので、彼に代わる総大将を五大老から立てる事を勧め、三成もこれに従った。
勿論状況的にも白羽の矢が立ったのは毛利輝元と宇喜多秀家であった。
前述した様に、本来、当主輝元を支える筈の者達は各々の考えが違い過ぎ、先手を打ったのは安国寺恵瓊だった。
安国寺は輝元を説得し、輝元は他の一門の者達や重臣に相談することなく総大将就任を受諾し、慶長五(1600)年七月一七日、石田三成・長束正家・増田長盛等に擁されて大坂城西の丸に入った。
吉川広家は出雲から上方に向かう途中で安国寺の使者と会い、輝元の西軍総大将就任を知り、慌てたが遅かった。
輝元は総大将就任後に徳川家康弾劾状を初めとする西軍総大将として発した書状に「安芸中納言輝元」と署名、花押を捺印する等、明らかに家康への敵対行為と取れる行動を取り続けた。
安国寺に先手を打たれる形になった広家は輝元の行動と、周囲の輝元に対する接し方に重大な危機感を抱いた。
そして、自分以外で家康に敵対するのを不利と考えていた益田元祥、熊谷元直、宍戸元次等が連名で黒田長政を通じて家康方の重臣である榊原康政・本多忠勝に弁疏したのだった。
関ヶ原の戦いにおいて家康が西軍諸将に数多くの調略の手を伸ばしていたのは有名だが、その手先として最も活躍したのが黒田長政で、父・如水譲りの謀略の才を持つ長政は広家の危機感は使える、と踏んだ。
この間も広家の「家康に対して勝ち目無し。戦うは不利。」との考えに変わりは無く、幾度と無く輝元に対して家康との不戦を説き、安国寺とも激論を交わしたが、既に周囲の状況がそれを許さなかった。
そこで安国寺が独断で密かに三成の要請に応える様に輝元を説き伏せた様に、広家もまた福原広俊以外の一族・重臣に知らせることなく、徳川方と不戦の密約を為し、徳川方からも井伊直政・本多平八郎忠勝の連名で血判付きの毛利家本領安堵状が返された。
いざ大坂城を出陣し、まずは家康の宿将・鳥居元忠が篭もる伏見城を攻めることとなり、総大将たる輝元は大坂城西ノ丸にて後詰となり、副将・宇喜多秀家率いる先遣隊には広家と秀元と安国寺が従軍することとなった(余談だが、広家の正室は宇喜多秀家の姉である)。
そして九月一五日ついに関ヶ原にて東西両軍は激突した。
関ヶ原の戦いは桃配山に陣した徳川家康率いる東軍を、正面にて石田三成、小西行長、島津義弘、宇喜多秀家、大谷吉継が迎え撃ち、東軍を取り囲む形で南西の松尾山には小早川秀秋が、東南の南宮山には吉川広家、毛利秀元、安国寺恵瓊、長宗我部盛親、長束正家が陣していた。
その西軍布陣は明治時代に陸軍学校に指南の為にドイツから招聘されたメッケル大佐が即座に「西軍の勝ち」と断じた程完璧なもの(の筈)だった。
だが周知の様に、三成からの出撃の狼煙を見ても南軍山に陣する西軍勢は動かなかった。否、動けなかったのである。
それは最前線に位置する広家が動かなかったからであった。
広家は決戦前日の九月一四日にも、福原、粟屋の両重臣の身内二人を人質として送り、併せて毛利の戦闘不参加を誓う書状を黒田長政に送っていた。
家康と戦う気満々の安国寺は、輝元の大坂入城前は消極的でもいざ戦場では勇猛だった毛利秀元に出撃を促したが、若く戦意盛んながらも毛利家の結束を重んじる秀元は前衛に位置する広家を出し抜くを良しとせず、更に後衛に位置する長宗我部・長束にも総大将毛利輝元の身内を出し抜く蛮勇は無かった。
一抹の不安を抱きつつ広家の元を訪れた安国寺は「弁当を食ったら出陣する!」と云って追い返された。
後年、この時の広家の虚言は、彼の官職名を持って「宰相殿の空弁当」と揶揄された。
毛利勢を初めとする南宮山の軍勢が一兵も動かないまま、周知の様に小早川秀秋の裏切りをもって関ヶ原の戦いは東軍の勝利に終った。
たが不戦の密約をした広家の仕事はまだ終ってなかった。
一応関ヶ原にて毛利勢が徳川勢と刃を交えるのは防いだとはいえ、当主・輝元が西軍総大将として大坂城に入城して西ノ丸に在り、西軍諸将に自らの名と立場で家康弾劾という明らかな敵対行為を取ったと云う既成事実があった。
これを何とかしなくてはならない、と考えた広家は合戦直後に黒田長政に使者を立て、前約確認の書状を送った。
一方、関ヶ原を引き上げた毛利軍内部では大坂城にて徹底抗戦か否かについて論議が交わされた。
秀元と立花宗茂は大坂城に篭もっての徹底抗戦を主張したが、ここで広家は初めて家康との密約が有ることを輝元に明かした。
九月一七日には黒田長政から福島正則との連名で輝元の元に「輝元は名目上の総大将に担ぎ上げられたに過ぎないから本領を安堵する」という内容の、万事が広家の取り計らった様に進んでいる旨の書状が届き、輝元は広家を褒めて主戦論を退けた。
そして感謝の返書を返し、二二日に大坂城を退去する旨を伝えた(実際の退去は二四日)。
ここに毛利家を徳川家康と戦わせまいとする吉川広家の目的は達せられた。
後は本領安堵の命を待つのみだったが……。
理不尽な反故 慶長五(1600)年一〇月一日に石田三成、小西行長、安国寺恵瓊が京都三条河原にて斬首され、先に近江で自害して果てた長束正家とともにその首を晒された。
だが勝者・徳川家康による論功行賞はここからが本番だった。
賞罰のいずれにおいても戦後処理の誤りは新たな紛争の火種となる。それは賞罰ともに軽過ぎても重過ぎても同様であった。
果たして、三成等の処刑の翌一〇月二日に毛利家に届いた書状は、吉川広家との密約を反故にするものだった。
黒田長政からのその書状には、密約の履行は「毛利輝元の西軍総大将就任が否応なしに担ぎ上げられた場合のみ」であり、大坂城から発見された西軍の連判状に輝元の花押があった事から毛利家の所領は没収の上、改易が免れないところである、と記されていた。
一方で吉川広家の家康に対しての異心なきは井伊直政、本多正信もよく承知で、毛利領の内、一、二ヶ国を与えるべく、ただいま家康に対して交渉中である、と記されていた。
当主・輝元の「身の安全」と「本領安堵」を約束に不戦に尽力した広家は宗家の本領安堵反故に愕然とした。
勿論自らが加増されるからといって喜べる話などでは断じてなかった。
広家には出雲一四万石から周防・長門の二ヶ国三七万石を与えるとの沙汰があったが、広家は自らに対する恩顧を謝しつつ、毛利家家名存続とを懇願し、万一輝元が徳川家に弓引く場合には本家といえども自らの手で輝元の首を取って差し出す覚悟である事を伝えまでした。
結果、一〇月一〇日に家康から輝元に対し、広家に与えられる予定の周防、長門の二ヶ国への大減封もってに毛利宗家安堵と毛利輝元・秀就父子の身命の安全を保障する旨の起請文がもたらされた。
輝元父子の命と大名としての家格が保てたとはいえ、丸で広家と家康との密約など無かったが如きの反故振りであった。
否、当初は丸で当て付けの如く、広家には二三万石もの大加増の沙汰で功績を褒めそやしたのだから、密約を承知の上で行った沙汰であるのは明らかであった。
こんな反故が罷り通ったのには二つの重要なポイントが有った。
そのポイントは反故にした徳川家康と、反故にされた吉川広家の双方に一つずつ有った。
一言で云えば前者は古狸の老獪さで、後者は家中の結束の無さであった。
つまりは広家は家康に嵌められるべくして嵌められたのであった。
勿論この謀略の害は広家一人の過失とは云えないものだった。
広家、秀元、恵瓊の意思分裂を当主・輝元がまとめ切れず、決断力を欠いたことと、各自が独断で動いた家中の結束の無さにあった(実際、広家と恵瓊は仲が悪かった)。
そして古狸の老獪さは家康が直接にではなく、井伊直政や黒田長政を使ったことにあった。
前述した様に、広家が交渉を行った相手は黒田長政・井伊直政がメインで、東軍総大将たる家康とは一度として直接交渉がなされていなかった。
家康は輝元が西軍総大将として「安芸中納言輝元」の署名と花押で西軍を動かし、四国、九州にも兵を向けたことを咎め、家康に対する異心あり、としたのであった。
つまり、広家の家康に対する忠義は忠義で受け止め、輝元の家康への敵対行為は敵対行為で断固罰するとの態度を取ったのであった。
密約にしても、行動に対する信賞必罰にしても、主君と家臣のいずれとのそれが重んじられるかを突く背景固めに家康の老獪さと、一枚岩の結束を図れなかったことに輝元・広家のみならず、秀元、恵瓊、福原、熊谷、その他諸々の毛利家中の落ち度があったと云える。
忌まわしき余波 関ヶ原の戦い論功行賞の結果として西軍についた大名家は五家が減封、九三家が改易となった。
特にともに五大老であり、一二〇万石の大身であった毛利・上杉は前者が周防・長門の三七万石、後者は米沢三〇万石という大減封を食らった。
毛利家中の徳川家への恨みは骨髄に達し、子々孫々に伝えられ、幕末に長州藩が早々に幕府を見限り、薩摩藩とともに倒幕の急先鋒となって、明治の藩閥政治を担ったのは有名である(実際、幕府に敵対したのは薩摩より長州の方が早かった)。
関ヶ原の戦いに前後して、徳川家のために痛い目を見た大名・小名の数は計り知れない。
だが、毛利家ほど恨みに思い続けた家も珍しい。
それは取りも直さず、徳川家康が吉川広家との密約を反故にしたことに根差したものであろう。
毛利勢が誰一人家康と和を請わず、戦い抜いた果ての改易や減封であったり、毛利家中一部の独断専行を咎めての小減封ならここまで恨まなかっただろう。
家康が輝元の行動をもって広家との密約を反故にするなら、毛利は毛利で家康の反故をもって徳川家への恨みとしたのであろう。真、反故とは個人の責任では済まされないものである。
毛利家の徳川家への恨みは骨髄に達し、子々孫々に残されたとはいえ、大減封直後の毛利家にはそのような余裕はなかった。
拙作・『隠棲の楽しみ方』にも記したが、輝元は表面上は剃髪して幻庵宗瑞と称して、家督を秀就に譲って隠居しつつも、裏では四分の一に減った禄高で必死に毛利家の再建に取り組んだ。
一般に愚将とされる毛利輝元だが、長州再建の手腕はなかなかに見事で、山代慶長一揆、吉見就頼の反乱など、減封に伴う混乱に苦しみつつも、これを逆に利用して大々的なリストラを敢行し、経費節約に努めた。
このリストラにしても昨今の三流企業が急場凌ぎに行う只の首切りではなく、一部には再興後の帰参を約束(実際に帰参した者も多い)し、その時の恩を感じていた長井治朗左衛門元房は輝元逝去の折に殉死し、輝元夫婦と同じ墓所に葬られた。
『隠棲の楽しみ方』にも記した様に、輝元は毛利秀元、益田元祥、宍戸元次等を手腕の引き出し・人事ともに上手く使いこなして新田開拓や特産品を奨励で長州藩の礎を築くのには申し分のない働きをした。
その辺りは自身が直接行動を取る際の能力よりも、人使いに優れていた父・隆元に似ていたのかも知れない。
だが、そんな必死の再建行政の中でも毛利家大減封への恨みは忘れられず、力で幕府に逆らえない現状でにおいてその矛先は皮肉にも毛利毛存続に尽力した筈の吉川広家(及びその子孫)に向けられた。
周防・長門の二ヶ国において、当主・毛利秀就が藩主を務める長州藩を本家として、その支藩に毛利秀元の長府藩(六万石)、毛利就隆(輝元次男)の下松藩(三万石。後に徳山藩と改名)が創設され、後には秀元三男の毛利元知を祖とする清末藩(一万石)が創設された。
だが、広家の所領・岩国は幕府からも領有を認められて三万石ありながら、広家は「領主」として「毛利家の陪臣」と位置付けとされ、岩国は最後の最後まで長州藩の支藩として認められることはなかった。
岩国は長州藩の本拠である萩から最も遠く、岩国以外の三家は支藩として正式に諸侯に列せられたが、勿論岩国は例外とされた。
その一方で岩国築城を許され、幕府からは大名としての扱いを受け、江戸に藩邸を構え参勤交代も行うと云う複雑な立場となった。
広家は報復人事や「主家を売った。」、「主家を貶めた」との陰口にも一切云い訳せず、沈黙を通し、元和の一国一城令に際しては幕府に許可されていた岩国城を破却し、広家没後も岩国吉川家では二代目から一一代目までの岩国領主の肖像画が描かれなかった。
主家を想っての行動が裏目に出たとはいえ、余りに報われない想いであった。
一方、関ヶ原の戦いでの毛利家のもう一人のブレーンでもあった毛利秀元は幼かった本家の藩主・秀就の後見を行い、輝元に代わって長州藩の執政となる一方で、継室(正室は豊臣秀長の娘)に徳川家康の養女(家康・異父弟松平康元の娘)を迎えて幕府との結び付きを強めつつ、家中では広家を「主家を売った者」と見做して冷遇する急先鋒となっていた。
秀元は関ヶ原の戦いにおける広家の観望反覆すなわち利敵・裏切り行為を厳しく咎めた。
だが、広家の主家への想いは全く理解されていなかった訳でもなかった様である。
毛利秀元は一時期、自藩の独立を考えた事もあり、その時には徳山藩だけではなく、岩国も声をかけており、長府毛利家と岩国吉川家とは後々共同歩調を取ることもあった。
また、広家の子で、吉見広頼の養子となっていた吉見政春は後に毛利姓を名乗ることを許されて「毛利就頼」と改名して長州藩一門家老の大野毛利家を創設してもいた。
毛利輝元、吉川広家、毛利秀元の祖父・毛利元就は「謀将」と呼ばれ、多くの大名・国人領主を嵌める一方で、吉川、小早川、宍戸(長女の嫁ぎ先)等の身内の結束は何よりも重んじた。
元就の遺言が軽んじられた訳はないだろうけれど、元就が期待し、創設した時ほどの結束があれば、徳川家康による反故も、その後の忌まわしき余波に、輝元も広家も幕府も曝されることはなかったかも知れない。
事実、毛利家中が力を合わせて取り組んだ内政は成功しているのである。
前頁へ戻る
冒頭へ戻る
戦国房へ戻る
令和三(2021)年五月二〇日 最終更新